天白遺跡の紹介
天白遺跡
遺跡の始まりは、縄文土器の出土から約7,000年前の縄文時代早期後葉です。その後空白の時期があり、弥生時代中期後葉から本格的に集落が形成されます。竪穴建物の数が一番多いことから、弥生時代中期後葉から後期前葉の時期が天白遺跡の最盛期であると考えられます。
古墳時代以降も集落は断続的に続きますが、奈良時代の8世紀前葉以降になると竪穴建物がみられなくなります。遺物の出土状況からその後は掘立柱建物など竪穴建物とは異なる形態の建物が建てられ、規模は小さいながらも古代から中世・近世も引き続き人々が生活していました。
発掘調査では、当時の人々が使用した土器や石器などが多く出土しました。また、当時は海に近い環境であったことから、竪穴建物跡のくぼみを利用して貝殻などを廃棄した貝層も見つかっています。これだけ多くの竪穴建物が見つかった集落遺跡は知多半島内では珍しく、知多半島および衣浦湾沿岸を代表する集落遺跡です。

天白遺跡・発掘調査風景

天白遺跡・貝層と土器の出土状況(該当部分を点線で表示しています)

天白遺跡・土器の出土状況(復元した土器を合成して表示しています)

天白遺跡・ヒスイ製勾玉
天白遺跡の概要についてまとめた解説です。参考にして下さい。
出土遺物は東浦町郷土資料館(うのはな館)で展示しています。
この記事に関するお問い合わせ先
観光交流課 郷土観光係(東浦町郷土資料館(うのはな館))
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字桜見台18-4
電話番号:0562-82-1188
観光交流課 郷土観光係へメールを送信




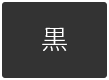

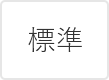
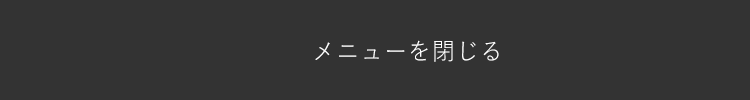
更新日:2022年03月01日