10月の自然環境学習の森日記
20日(日曜日)
「里山の秋を見つけよう」に参加しました。
東浦町の自然環境に詳しい知多自然観察会主催の「里山の秋を見つけよう」に参加しました。参加者は、地域の住民だけでなく命をつなぐプロジェクトの学生委員の参加もありたくさんの人が集まりました。
秋は、実りの秋とも呼ばれており、ドングリやオレンジ色の実が鮮やかなカラスウリ、色は地味だけど甘い実がなるミツバアケビ、ジャガイモのような味がするムカゴなどの実を見つけることができました。アキアカネなどのトンボもたくさん飛んでいたなど、まだまだ気温は高めでしたが、秋を感じることができました。


【ミゾソバ(ナデシコ目タデ科)】
水辺などでよくみられる植物。葉の形が牛の顔に似ていることから「ウシノヒタイ」や、花の形から「コンペイトウクサ」と呼ばれています。名前の由来は、葉の形がそばの葉に似ており、田んぼの溝などでよく生えることから、この名前が付いたと言われています。

【オオカマキリ(カマキリ目カマキリ科)】
開けた野原より林の縁などでみられる大型のカマキリ。大きな鎌で他の昆虫を捕まえて食べるが、ときにはカエルやトカゲなどの昆虫以外もエサとして食べます。
4日(金曜日)
今年も良く実っています。
自然環境学習の森には、コナラやアベマキなどの実のなる木がたくさんあります。その中でも特に人気があるのが栗の木です。今年もたくさんの栗が実っています。
栗の実やドングリなどの木の実は、野生動物の貴重な食糧となります。鳥やネズミ、ウサギやキツネなどはドングリが大好物です。ドングリなどの木の実を求めて動物たちが自然環境学習の森へやってくるかもしれません。

【栗(ブナ目ブナ科)】
里山でみられるクリの多くは、栽培品種であり、自生しているクリに比べ実が大きくなります。一般的に自生しているクリは、「シバクリ」や「ヤマグリ」と呼ばれています。なお、自然環境学種の森のクリは、栽培品種であり、大きな実が生ります。

【ハラビロカマキリ(カマキリ目カマキリ科)】
緑色が鮮やかなちょっと短く太めのカマキリです。自然環境学習の森では、草地より樹木の多い場所でよく見かけます。

【アメリカザリガニ(エビ目アメリカザリガニ科)】
ウシガエル(食用ガエル)のエサとして日本にやってきたアメリカザリガニ。トンボのヤゴやメダカなどの小型の水生生物を食べてしまうため、厄介者になっています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境保全係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
環境課 環境保全係へメールを送信




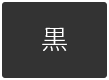

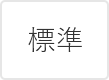
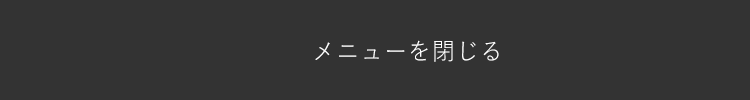
更新日:2020年02月07日