4月の自然環境学習の森日記
27日(木曜日)
フジの花がきれいに咲きました
自然環境学習の森には、フジが自生しており、今年も薄い紫の花を咲かせました。このフジは、公園などで見られるものと異なり、近くに生えているコナラなどの樹木に巻き付き、上は上へと伸びていきます。巻き付かれた木は大変ですが、上に伸びていくフジの花はとてもきれいに見えます。
野生のフジも公園などで見られるフジに負けないくらいきれいに咲きますので、一度見に来てはいかがですか。


「ミドリハコベ」
アシ原を刈り取った場所では、背丈が低い小さな白い花が咲いていました。アシが生えているときは気が付きませんでしたが、アシ原には、アシだけでなく「ミドリハコベ」のような小さな植物も生えています。

「ゲンゲ(別名:レンゲソウ)」
別名のほうが有名で、本当の名前を知らない方も多いと思います。田んぼなどの畔によく咲いているきれいな花です。
8日(土曜日)、23日(日曜日)
4月8日(土曜日)、23日(日曜日)に里山の保全活動と竹の子掘りを開催しました。今年も昨年と同じく暖かな春らしい陽気の中で活動を行いました。
竹の子を掘る前に里山の保全活動を行います。竹の子は、竹林が適正に管理できていないとよい竹の子は採れないので、自然環境学習の森で日ごろから行っている保全活動の一つである、伐採した竹の運び出し作業を行ってもらいました。気温が高かったこともあり、参加者のみなさんは汗をかきながら作業を行っていました。
1時間作業を行った後は、いよいよ竹の子掘りです。しかし、今年は3月に雨が少なかったせいか、竹の子の数が少なく、竹の子を掘る時間より探している時間のほうが長かったが、それでも1グループ3~5本程度採ることができました。
里山の保全活動に興味を持ってもらうために、来年もイベントの開催を予定しているので、是非ご参加ください。


バケツリレーのような方法で、竹をポーラス炭を作成する場所へ運び出しました。

竹の子掘りでは、大きな竹の子が採れました。写真ではわかりにくいですが、大人が両手で抱えるほど大きな竹の子でした。私もこれほど大きな竹の子は、初めて見ました。
22日(土曜日)
「東浦の自然に親しむ観察会(春の竹林を探検しよう)」を開催しました。4月の上旬から5月の中旬ごろは、新緑がきれいな時期で、様々な色合いの緑を見ることができます。どんぐりの木で有名な「コナラ」は、この時期に葉と同時に花を咲かせます。参加者のみなさんも初めて見た方がほとんどで、「花に見えない」などの感想がありました。
また、生き物も活発に活動を始める時期であるため、蝶やカメ、カエルなど37種類の生き物を観察することができました。


「ミシシッピアカミミガメ」
子ガメが鮮やかな緑色をしていることから「ミドリガメ」として親しまれていますが、寿命が長く、成長が早く、性格が獰猛になることから、川や池に捨てられることにより、日本の各地で数を増やしているカメです。大食で様々な生き物を捕食してしまうため、問題となっています。

「ジャコウアゲハ」
ウマノスズクサがある草原で見られる大きなチョウで、アゲハチョウより羽ばたきが少なく優雅に飛ぶことが特徴である。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
環境課 環境マネジメント係へメールを送信




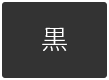

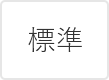
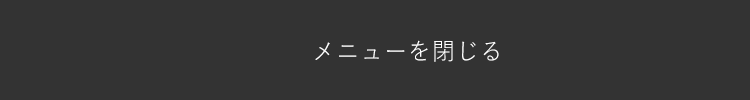
更新日:2017年04月28日