7月の自然環境学習の森日記
30日(日曜日)
「東浦の里山にメダカを復活させよう」を開催しました。
東浦自然環境学習の森には、小川が流れており、この水を利用して稲作が行われています。この小川には以前メダカが住んでいた記録がありましたが、現在ではメダカは住んでいないだけでなく、生物もあまり住んでいない貧相な小川となっています。
そこで昨年度からメダカが住める小川を作り、メダカを復活させる講座を開催しています。参加者は保護者含めて17名が集まり、水質調査や生物採集、メダカの放流を行いました。生物採集は、昨年度3種類しか生き物を捕まえることができませんでしたが、メダカを含む6種類の生き物を捕まえることができました。
参加者は、メダカをきっかけに里山の環境と生物多様性について学ぶことができました。


温度計や透視度計、パックテストを使用して水の評価をしてもらいました。

今年も講座終了後石ヶ瀬川産のニホンメダカを放流しました。
12日(水曜日)
知多市の「竹林づくり講座」受講生が視察研修に訪れました。
知多市の緑と花の推進課が開催している「竹林づくり講座」の受講生26名が、自然環境学習の森の里山保全活動の視察に訪れました。知多市も以前より市内の竹林を適正に管理していくために、「竹林づくり講座」を開催しており、講座内で竹林管理方法やさまざまな地域へ視察研修を行っています。
「竹林づくり講座」の受講生は、竹林管理作業を実際に行ったことがある方から、これから始める方までさまざまな方が参加していました。まずは、東浦自然環境学習の森の概要について説明し、その後実際に活動している現地を見ていただきました。東浦自然環境学習の森での竹林保全活動には、竹林部会の田中会長が説明し、その後受講生との意見交換を行っていました。私たちにとっても意見交換や情報交換ができたため、より良い機会となりました。


講座開催日は、曇り空でしたが湿度が高くとても蒸し暑い日となりましたが、参加者はメモを取りながら熱心に話を聞いていました。

竹林部会では、保全活動で伐採した竹を活用して竹炭づくりを行っています。竹林整備は、伐採後の竹の処分が大変であるため、利活用を考えながら活動することが大切であると説明していました。
8日(土曜日)
「初夏の里山で生き物を探そう」を開催しました。
朝から日差しがギラギラと照らすとても暑い日となりましたが、「初夏の里山で生き物を探そう(東浦の自然に親しむ観察会)」に23名の参加者が集まりました。夏の生き物でもっとも人気がある生き物がカブトムシです。東浦自然環境学習の森にもカブトムシが好む、コナラやクリの木があるため、立派なカブトムシが生息しています。
本日、集まった多くの参加者は、もちろんカブトムシを捕まえることが目的です。カブトムシが集まるポイントに到着すると、他の虫たちがたくさん集まっていました。しかし、採集時に注意が必要なのは、スズメバチです。観察会当日もカブトムシが集まる木にたくさんのスズメバチが集まっていました。観察会では、カブトムシの他にも38種類の生き物を観察することができ、カブトムシを見つけることができなかった参加者もとても喜んでいました。


「カブトムシが集まる木」
コナラなどの木は、カブトムシが大好きな樹液を出します。その樹液を食べにカナブンやスズメバチも集まっていました。

森林以外にも水辺や湿地帯、竹林などで生き物を探しました。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
環境課 環境マネジメント係へメールを送信




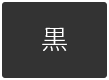

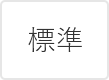
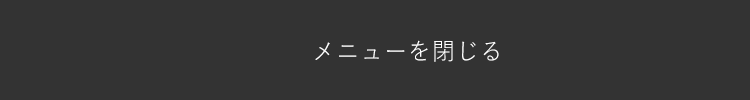
更新日:2017年08月09日