4月の自然環境学習の森日記
20日(月曜日)
ハナニラがきれいに咲いていました。
春の自然環境学習の森では、星の形をした薄むらさき色の花を見ることができます。これは、「ハナニラ」と呼ばれ、一度はどこかで目にしたことがある方も多いと思います。
ハナニラは、明治時代に園芸植物として日本にやってきた植物で、原産地は南アメリカです。葉や根を傷つけると、ニラやネギの匂いがするため、この名前が付いたと言われています。

日本の在来種ではありませんが、「スプリングスター(英名)」などという名前で、一般的に園芸種としても親しまれています。

「ヒメオドリコソウ(シソ科)」
花の形が笠をかぶった踊り子の姿に似ているため、この名前が付いたと言われています。
ヨーロッパ原産で、明治時代の中期に東京で初めて見つかりました。自然環境学習の森でも、散策路や木道付近で観察することができます。
13日(月曜日)
今年もきれいに咲きました。
自然環境学習の森では、春になると様々な植物が花を咲かせます。特にあずまやの近くには大きなヤマザクラの木があり、今年もとてもきれいな花が咲き、私たちを楽しませてくれます。
サクラは、野生として生息していた原種のサクラと、この原種を交配して作られた里桜の大きく二つに分けることができます。ヤマザクラは、原種のサクラの代表格で寿命も長く、100年から300年程度生きると言われています。江戸時代までの花見は、このヤマザクラを鑑賞していたと言われており、江戸時代末期に「ソメイヨシノ」が人工交配されてできると、花が咲いたあとに葉がつくことや管理のしやすさなどの理由から人気となり、全国に広がっていきました。
ソメイヨシノもきれいな花を咲かせますが、昔から里山の春を彩ってきた、ヤマザクラもとてもきれいだと思いました。

ソメイヨシノより、薄いピンク色の花を咲かせます。

【トウカイタンポポ(キク科)】
道端で見かけるタンポポの多くは、セイヨウタンポポ(外来種)となってしまいましたが、自然環境学習の森ではこのトウカイタンポポ(在来種)が優先種(数が多い)となっています。花びらの付け根が反り返っていないことから、セイヨウタンポポと見分けることができます。

【セイヨウタンポポ(キク科)】
花びらの付け根が反り返っています。こちらがセイヨウタンポポです。タンポポを見つけたら、日本のタンポポか外国のタンポポか調べてみるのも楽しいですね。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
環境課 環境マネジメント係へメールを送信




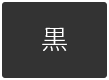

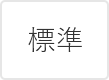
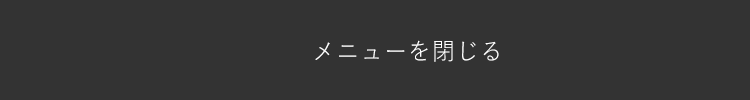
更新日:2020年08月18日