11月の自然環境学習の森日記
30日(月曜日)
ヨシを使った巣
皆さんは、カヤネズミを知っていますか。
カヤネズミは、親指ほどの大きさで体重も500円玉ほどしかない日本で一番小さいネズミです。カヤネズミは、カヤなどの背丈の高いイネ科の植物を利用して巣を作ります。東浦自然環境学習の森では、ヨシ原に生息しており、ヨシを利用して写真のような球状の巣を作ります。
カヤネズミは、現在絶滅危惧種に指定されていますが、数が減少している大きな理由が草地の減少です。温暖で湿潤な日本では、森林が発達しやすく、自然条件下で草地ができるのは河川や湿地などの樹木が育ちにくい場所のみであり、その他の場所は時間が経過するにつれて草地は森林に代わっていきます。昔の人々の生活には草地が無くてはならない場所となっており、草を刈り取り屋根や壁材に利用したり、家畜の餌にしたりと生活に利用してきたため、草地がところどころにありましたが、今では限られた場所にしかなく、カヤネズミの住める環境が減ってきていることが、生息数を減らしている理由となっています。
東浦自然環境学習の森では、毎年3月にヨシ原の刈り取りを行い、火入れ作業をすることで、良好な草地を管理しています。カヤネズミが住める環境を今後も守るために活動を続けていきたいと思っています。

【カヤ玉(カヤネズミの巣)】
カヤネズミを守るために草地の保全活動を行っていますが、とても小さなカヤネズミを見つけるのは、難しいです。このカヤ玉は、カヤネズミが住んでいる証拠になるので、保全活動を続けて行く励みになります。
18日(水曜日)
シイタケが生えてきました。
東浦自然環境学習の森では、森林の保全活動として剪定や伐採した樹木を利活用して、シイタケ栽培を行っており、2年前にシイタケの駒菌を打ち付けた伐採木から立派なシイタケが生えてきました。
シイタケは、名前のとおりシイの木になるきのこですが、自然環境学習の森にはシイの木は生育していないため、同じブナ科の植物であるコナラの木で栽培しています。
原木シイタケの栽培は時間がかかり、菌を付けてから2年程度時間がかかります。10月の気温が下がり始めたころより生え始め、今がちょうど最盛期のようです。

国内で生産されるきのこの90%が菌床(オガ屑などを固めた20センチメートル四方ほどのブロック)栽培です。原木シイタケは、菌床シイタケに比べ、風味や香り、肉厚さにが優れていると言われています。

【ハラビロカマキリ(カマキリ科)】
森を散策しているとハラビロカマキリを見つけました。ハラビロカマキリは5月~11月頃まで見ることができ、本州から九州まで幅広く生息しています。オオカマキリよりも小さく腹部が太くなっているため、オオカマキリよりもかわいらしく見えます。

【ヨシ(イネ科】
休耕田などの湿地にすぐ繁殖するため、厄介者の印象が強い植物ですが、かつては「すだれ」や「屋根材・燃料」などに利用され、生活になくてはならない植物でした。東浦自然環境学習の森では、「オオヨシキリ」や「カヤネズミ」などの生き物が生息する生物多様性豊かな場所となっているため、ヨシが群落で生えるヨシ原の保全活動が行われています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
環境課 環境マネジメント係へメールを送信




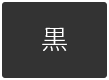

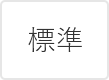
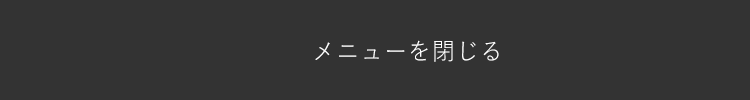
更新日:2021年01月08日