第2回東浦町の環境を考える会ワークショップ
第2回目は、第1回目の3つのテーマを基に、それぞれのグループのテーマの課題とそれを解決するための取り組みを3つの視点で話し合いました。

開催概要
| と き | 令和2年1月12日(日曜日) 午前10時から |
|---|---|
| と こ ろ | 東浦町勤労福祉会館 |
| 参加者 |
町内で環境活動に取り組む団体の代表者、自治会代表、 町内企業で環境活動に取り組む担当者、公募委員 計17名 |
| ファシリテーター | 高野雅夫 氏(名古屋大学大学院環境学研究科教授) |
| 内 容 |
(1)環境問題の歴史 (2)グループワーク 「課題」と「取り組むべきこと」の整理 (3)グループ発表 |
低炭素社会グループ


|
課題 |
取り組むべきこと |
||
|
住民 |
企業 |
行政 |
|
〈啓蒙〉〇低炭素社会について理解を深める 〇炭素発生を減らすためのチカラは一人では微力 〇低炭素に向けてのテーマが思いつかない |
〇コミュニティでの集まりで低炭素社会を取り上げ、意識を持たせる
|
〇商工会で「省エネ機器」「ごみ分別」「地産地消」に取り組む 〇家電では消費電力がわかるように、どれだけ低炭素なのか「見える化」していく |
〇何をすれば低炭素社会が推進できるのか、企業や住民にチラシやポスターで啓蒙する 〇低炭素社会について理解が深まるように、補助金などを出しつつ、興味をもってもらう |
〈すぐにできること〉〇太陽光発電の設置 〇交通渋滞を無くす、減らす 〇森を減らすのではなく植林する 〇ごみの減量、マイバックを進める |
〇ごみの減量のためによく考えて購入する 〇廃プラの分別強化に協力する |
〇低炭素の設備に転換する 〇個人が消費する商品を低炭素型製品にする。開発する 〇ごみの分別を徹底する |
〇エコハウスに建て替えさせる施策を行う 〇渋滞解消に向けての道路整備を推進する 〇補助金を拠出する |
〈すぐできないこと〉〇水素利用が進まない 〇ごみから資源・エネルギーを作ることができているか? 〇エコカーの購入が進まない 〇省エネ機器の購入が進まない |
〇お金が多少かかってもエコハウスを建てる。みんなの想い |
〇再生可能エネルギーの使用率の向上 〇儲けて納税する |
〇省エネ工事の補助金を出す 〇水素ステーションを設置する 〇電気充電スタンドを設置する 〇廃プラの分別、洗浄設備を導入する |
循環型社会グループ


|
課題 |
取り組むべきこと |
||
|
住民 |
企業 |
行政 |
|
〈ごみの減量〉〇ごみの総量の減量、リデュース 〇廃棄物をリサイクルにより減らすにはどうすればよいのか? 〇ごみを回収する手段・方法がない(特に粗大ごみ) |
〇環境の取組をたくさんの人に知ってもらい、理解してもらうことが大事 〇分別指導員制度を作り、出し方を住民に徹底させる 〇ごみゼロ運動を毎月行う |
〇CO2排出量を削減させるには、産業部門の努力が大
|
〇地域と役場が一体化した環境の取組 〇ごみ袋の有料化 〇大型ごみの回収回数を増やしてほしい 〇タバコのポイ捨て禁止条例をつくる |
〈分別のための教育〉〇理解活動、分別教育 〇みんなが環境について意識を高めなくては 〇環境をよりよく変化していくための行動とは何か |
〇子ども(幼児期)からの 分別を教える。 〇白色トレイの回収サービス 〇PSレス(ポリスチレン) |
〇社会教育、分別ルール
|
〇多言語での分別ルールの周知
|
〈再利用のための情報公開、コミュニケーション〉〇リユースの流れを作り、運用 |
〇フリーマーケット、メルカリなど 〇メルカリを世代が違う人にも周知し、みんなでサービスを使う |
〇ゼロエミッション活動 |
〇粗大ごみの家庭引き取り回収サービス 〇車を利用できるサービス |
〈環境美化〉〇公道の美化、雑草や土砂をなくす 〇コンビニ付近にごみのポイ捨てが多い 〇環境と生き物・人間の健康関連PR |
〇イベントでごみ拾い |
〇環境美化、清掃活動への協力 〇ガードレール周辺の草刈りをする 〇コンビニに直接協力を求める |
〇川の整備(川の中の木を切る) 〇ごみの分別はしっかりできている(一部を除いて) |
自然共生社会グループ


|
課題 |
取り組むべきこと |
||
|
住民 |
企業 |
行政 |
|
〈里山対策〉〇里山がなくなり、住宅に変わっていっている 〇里山のPR不足 〇里山・公園の木のせん定 〇竹林が増えている 〇耕作放棄の畑の問題 〇ロードキルを防ぐ |
〇自治会の協力 〇住民ボランティアの協力 〇コミュニティで河川のごみ拾いをする 〇里山保全ボランティアグループを作る |
〇団体での参加・協力 〇資金面での協力 〇トラックの無料貸し出し |
〇ごみ袋の無料化 〇落ち葉・竹枝の集積場を作る(リサイクル) 〇竹枝等の処理料の無料化 〇竹枝等の運送トラックの無料貸し出し 〇駐車場、アクセスの充実 |
〈東浦の生物多様性〉〇自然共生に対しての住民の意識を高める 〇外来種の駆除 〇外来種の植物の把握 〇東浦の在来種を実際に見てみたい 〇野生動物対策 |
〇観察会への参加 |
〇団体での参加・協力 〇資金面での協力 〇トラックの無料貸し出し
|
〇外来種のPR 〇農免道路にアニマルパスを作る
|
〈道路・河川の管理〉〇池の生き物調査 〇自然観察ための駐車場が川の近くにない 〇東浦の川の汚れ 〇川、海洋、道路のごみ 〇道路側の樹木の茂り |
〇自治会の協力 〇住民ボランティアの協力 〇コミュニティで河川のごみ拾いをする 〇里山保全ボランティアグループを作る |
〇団体での参加・協力 〇資金面での協力 〇トラックの無料貸し出し
|
〇「できない」ではなく「できる」方法を考えてPRする。 〇住民と企業の橋渡し 〇ごみ袋の無料化 〇駐車場、アクセスの充実
|
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
環境課 環境マネジメント係へメールを送信




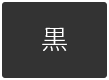

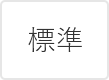
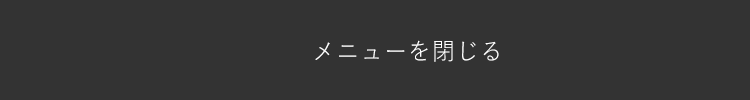
更新日:2020年02月04日