飛山池の森
森の樹々
飛山池の囲む森では、最上層をコナラとクスノキが占め、ムクノキやタブノキの大木が所々で最上層に顔を連ねており、その下の亜高木層をカクレミノとヒサカキが占め、ヤブニッケイ、クロガネモチ、タブノキ、カラスザンショウ、ハゼノキ、リョウブなどが負けじと葉を茂らせています。その下の低木層にはイヌビワ、ムラサキシキブ、コウゾ、センリョウ、マンリョウなどがいます。ヤマフジやアケビのような蔓性の植物もところどころに見られます。
知多半島の原生林はシイノキやカシが主体の照葉樹林でした。農耕が始まると森を燃料や肥料の資源として利用するようになりコナラなどが主体の落葉広葉樹林に変化しました。
そしてその落葉広葉樹の森であった自然林が、昭和の高度経済成長期以降人の手が入らなくなり、知多半島の本来の森である常緑広葉樹の原生林に戻ろうとしています。散策路を備えた飛山池の森はその過程を間近に見れる数少ない森の一つとなっています。
そんな飛山池に今現在どんな植物がいるのか調べてみています。
高さも太さもある大きな樹(幹周150センチメートル以上)
- サクラ

- バラ科サクラ属の落葉高木。幹周234センチメートル(分枝0.3メートル 2023時点)のもの有り。この樹は根本から少し上がったところで4本に分かれている。1本立ちのものも幹周が150センチメートルを超える樹が多い。散策路沿いにいる大きな樹はオオシマザクラで、池の水際近くのものはヤマザクラが多い。
- 東浦町に限らず知多半島の森の中にはポツリポツリと野生種が生えており、春になると突然桜色の樹冠がいくつも現れ、桜好きの目を楽しませてくれている。


- コナラ

- ブナ科コナラ属の落葉高木。幹周213センチメートル(1.3メートル 2023時点)のもの有り。幹周が150センチメートルを超える樹が多数有り。飛山池では、亜高木層を占める常緑広葉樹に抑えられているのか、幼樹をほとんど見ない。
- 東浦町では、普通に見られる樹種。雑木林には必ずいるドングリの樹。薪を燃料としていた時代には重要資源。シイタケのほだ木としても利用される。

- ムクノキ

- アサ科ムクノキ属の落葉高木。幹周205センチメートル(1.3メートル 2023時点)のもの有り。大きな樹が1本とそれに準ずる大きさの樹が数本有り。まだそれほど太くは無い樹が数本と芽吹いて間もない幼樹が多数見られる。
- 東浦町では、所々見られる樹種。例えば三重県津市の椋本の大ムクのような樹齢1500年という巨木も存在する長命の種族。果実は小鳥に人気が高い。
- タブノキ

- クスノキ科タブノキ属の常緑高木。幹周198センチメートル(分枝1.3メートル 2023年時点)のもの有り。大きな樹が1本とそれに準ずる太さの木が1本有り。まだそれほど太くは無いが、亜高木層を形成している樹が数本有る。
- 2024年2月、幹周246センチメートル(分枝0.4メートル 2024時点)のものを発見。
- 東浦町では、時々見られる樹種。本種も数百年以上生きる長命種。近いところでは豊橋市の熊堅大神社のタブノキ(推定樹齢200年以上、幹周385センチメートル)や名古屋市の御園のタブノキ(樹齢約250年[2019年時点]、幹周3.8メートル)がある。
- クスノキ

- クスノキ科ニッケイ属の常緑高木。幹周185センチメートル(1.3メートル 2023時点)のもの有り。大きな樹が多数有り。まだそれほど太くは無い樹や芽吹いて間もない幼樹が多数見られる。
- 東浦町では、コナラ同様よく見られる樹種。於大公園には地際の幹周が475センチメートル(分枝 0.3メートル 2023時点)の大きなクスノキが有る。
- クロガネモチ

- モチノキ科モチノキ属の常緑中高木。幹周161センチメートル(1.3 メートル 2023時点)のもの有り。まだそれほど太くは無い樹がところどころに見られる。
- 東浦町では、植栽も含めて多数見られる。雌雄異株で秋になると雌株には直径5ミリメートル程の赤い果実が多数ついて目を惹く。
高さのある大きな樹(幹周150センチメートル以下)
- アラカシ

- ブナ科コナラ属の常緑高木。幹周は91センチメートル(分枝1.0 メートル 2024時点)でそれほど大きくないが、光を求めて横に伸びた枝が極端に長い変わった樹形の個体がいた。枝の長さは6メートルほどで周長は43センチメートル。飛山池の森にはアラカシは少ない。
- 東浦町では、よく見られる樹種。植栽として使われることが多く、ところによってはたくさん見られる。
- エノキ

- アサ科エノキ属の落葉高木。幹周141センチメートル(1.3 メートル 2023時点)のもの有り。飛山池の森にはエノキは少ない。
- 東浦町では、コナラやクスノキ同様よく見られる樹種。ムクノキ同様長命の種族でムクノキより個体数は多い。
- スギ

- ヒノキ科スギ亜科スギ属の常緑針葉樹。幹周109センチメートル(1.3 メートル 2023時点)のもの有り。飛山池では、北側入口の近くに数本と森の中に1本見られる。
- 東浦町では、ほとんど見ない樹種。時々見られるものは植栽の可能性が高い。
- ヒノキ

- ヒノキ科ヒノキ属の常緑針葉樹。幹周79センチメートル(1.3 メートル 2023時点)のもの有り。飛山池では、北側入口の近くに数本見られる。
- 東浦町では、ほとんど見ない樹種。時々見られるものは植栽の可能性が高い。
- モチノキ

- モチノキ科モチノキ属の常緑中高木。幹周73センチメートル(1.3 メートル 2023時点)のもの有り。飛山池では、クロガネモチに比べて数が少ない。
- 東浦町では、時々見られる樹種。雌雄異株で、株単位で性転換する特性があるとのこと。雌株は、秋に直径1センチメートルほどの赤い果実を多数つけ目を惹く。樹皮から鳥黐を作ることからモチノキの名がついたとされる。
- ヤブニッケイ

- クスノキ科クスノキ属の常緑高木。飛山池では、幹周が1メートルを超えるものはいないが、数は多く幼樹から林冠に届く大きなものまで有る。
- 東浦町では、時々見られる樹種。葉の三行脈が目立ち、ちぎると微かにニッキの匂いがする。葉のつき方にも特徴があり、枝にほぼ等間隔で並んでつき、対生と互生が混ざっている。
- センダン

- センダン科センダン属の落葉高木。飛山池では東エリア、西エリアとも散策路入り口付近に大きな樹が1本ずつある。西エリアのものは幹周146センチメートル(1.3 メートル 2024時点)、東エリアのものは幹周129センチメートル(1.3 メートル 2023時点)。
- 東浦町では、よくみられる樹種。初夏には淡い紫の花が、冬には黄色い実が目を引く種族。南方熊楠が好んだことでも知られる。数百年を生きる長命な種族で徳島県阿波市の「野上の大センダン(幹周8メートル 2008時点)」と香川県仲多度郡の「琴平町の大センダン(幹周7.4メートル 2013時点)は国の天然記念物に指定されている。


- イヌマキ

- マキ科マキ属の常緑針葉樹。飛山池では西エリアに数メートルの高さのものが1本有り、それ以外は2メートルに満たない小さなものが多数見られる(2024時点)。飛山池に侵入してまだ間がない様子。
- 植栽としてよくみられる樹種。東浦町でも果樹園の周りの防風林として植えられているものをよく見る。熟すと赤くなる種托とその先に付く緑色の種子の様子が印象的な種族(ちなみに、種托部分は可食だが、種子は有毒で食べれない)。また、種子がまだ樹上にある時から発芽する胎生種子を作ることでも知られる。
- シュロ

- ヤシ科シュロ属の常緑高木。飛山池では、まだ大きな樹は無いが、高さが1メートルに満たない小さな樹が多数見られる(2023時点)。イヌマキ同様、侵入してまだ間がない様子。
- 東浦町では、植栽されたものが公園などで見られ、おそらくその種子が鳥に運ばれて野生化したものが森の中に見られる。温暖化に伴い生息域を拡大していると言われている。元々は、平安時代に九州に持ち込まれた外来種。
- モウソウチク

- イネ科マダケ属の常緑高木。飛山池では、東と北の駐車場入り口付近に群生している。
- 知多半島全域の至る所で見られる。中国大陸原産。筍はエグ味が少なく食用になる。繁殖力が非常に強く、他の樹種を駆逐してしまうほどで、竹害が問題になっている。
中くらいの高さの樹
- カクレミノ

- ウコギ科カクレミノ属の常緑亜高木。幹周141センチメートル(1.3 メートル 2023時点)のもの有り。飛山池では、ヒサカキ同様非常にたくさん見られる種族。
- 東浦町に限らずこの地方では至る所で見られる樹種。

- カラスザンショウ

- ミカン科サンショウ属の落葉高木。幹周66センチメートル(1.3 メートル 2023時点)のもの有り。飛山池では、散策路沿いに多く見られる。
- 東浦町では、所々で見られる樹種。非常に鋭い棘が幹から花柄までたくさん生えていて、危険な香りのする樹。
- クサギ

- シソ科クサギ属の落葉小高木。飛山池では、芽吹いて間もない幼樹が散策路沿いに散見される。
- 東浦町に限らずこの地方では至る所で見られる樹種。触れると独特の臭気を放つ、その名にし負う種族。ただ、花は見た目も愛らしく良い香りがし、藍色の実と赤色の萼片で構成された色鮮やかな果実がなるので、思いのほか人気がある。

- ハゼノキ

- ウルシ科ウルシ属の落葉小高木。飛山池では、比較的多く見られる樹種。高木層に届きそうな大きな樹から芽吹いて間も無い幼樹まで色々な大きさのものが有る。
- 東浦町では、森の中以外でもよくみられる樹種。果実は小鳥に人気が高い。紅葉が美しいことでも知られている。


- ヒサカキ

- モッコク科ヒサカキ属の常緑小高木。飛山池では、カクレミノと同等かそれ以上に多くみられる樹種。
- 東浦町では、森の中では必ずと言ってよいほど良く見られる樹種。花の独特の香りが春を告げる風物詩となっている。

- ビワ

- バラ科シャリンバイ属の常緑小高木。飛山池では2023年時点で小さな樹が1本見られた。
- 東浦町を含めたこの地域では、植栽をよく見るが野生化したものもよく見られる樹種。冬に花が咲き初夏に果実が熟すという珍しい生活環を持つ種族。見た目が地味であまり目立たないがとても良い香りのする白い花をつける。冬のある日、見るより先に突然漂ってくるその香りで開花を知らせる。
- アカメガシワ

- トウダイグサ科アカメガシワ属の落葉小高木。飛山池では散策路沿いに散見される樹種。
- 東浦町では、非常によく見られる樹種。日当たりの良い道沿いや林縁に若木が列をなして群生していることもある。名前の通り、春の若葉が綺麗な赤色をして目を惹く。


- リョウブ

- リョウブ科リョウブ属の落葉小高木。飛山池では東エリアに群落有り。リョウブは幹の上部と下部で樹皮の模様が異なり、上部はマダラ模様になり、下部は縦に裂けて剥がれる特徴があるが、飛山池のものは幹のかなり上の方まで樹皮が縦長に割ける傾向が強く、一見するとシャシャンボの様に見える。
- 東浦町では、森の中に時々見られる。
- クロバイ

- ハイノキ科ハイノキ属の常緑小高木。飛山池では東エリアに1本かなり背の高い大きな樹が有る(2024時点)。葉や花はその上部にあって見え難いので気づき難いが、4月中旬以降の花の時期にその良い香りと落ちている花冠で本種と知れる。幼木も見られる。
- 東浦町では、稀に見られる樹種。花のない時期には、ヒサカキなど他の常緑小高木に紛れて見つけ難いが、花が咲くと一気にその存在を知らしめてくれる。

- シャシャンボ

- ツツジ科スノキ属の常緑小高木。飛山池では、南エリアと西エリアにシャシャンボとしては大きな樹が数本見られる(2024時点)。他の高木に上を抑えられているせいか、窮屈そうに生えている。
- 東浦町では、森の中に時々見られる。ブルーベリーと同属で、果実が食用になる。樹皮が縦に裂けて剥がれるので、特徴的な見た目になる。そのため、大きな樹では葉を見るより先に樹皮で存在が知れる。葉の裏側、主脈に沿って突起があることも見分ける時の目安になる。
小さい樹
- マンリョウ

- サクラソウ科ヤブコウジ属の常緑低木。飛山池では散策路沿いに散見される。樹高は数十センチメートルほどの小型のものばかり(2024時点)。
- 東浦町では、林の縁や中の通路沿いによく見かける。ヒョロヒョロと直立した幹の上のほうに葉が集中している樹形と波型で尖らない鋸歯が独特な葉の形で、一度覚えてしまうとすぐに見つけられる樹種。実は葉の下につく点も特徴的。冬に実る赤い実と名前から正月の縁起物として人気がある。品種改良も盛んで、いわゆる古典園芸植物の一つ。波型の鋸歯に謎多き葉粒菌が共生していることでも知られる。
- ムラサキシキブ

- シソ科ムラサキシキブ属の落葉低木。飛山池では散策路沿いに数本見られる。
- 東浦町では、林の中に時々見られる樹種。綺麗な紫色の実がなることで知られ、園芸品種も多い。6月ごろに咲く花も紫色で綺麗。材は緻密で硬いのでノミの柄に使われたとのこと。
- センリョウ

- センリョウ科センリョウ属の常緑低木。飛山池では、東のエリアに多く、果実の黄色いキミノセンリョウもいる。
- 東浦町では、マンリョウ同様林の縁や中の通路沿いによく見かける。鋸歯らしい鋸歯のある4枚の葉が十字対生し、その上に花や赤い実がつく様子がマンリョウとは対照的な特徴。マンリョウ有るところセンリョウ有り、センリョウ有るところマンリョウ有り、と言っても良さそうなくらいよく似た環境で見かける。そして、マンリョウ同様、冬に実る赤い実と名前から正月の縁起物として人気がある。センリョウ科は、古草本類の仲間で最も原始的な被子植物の仲間といわれている。花には花被(花弁と萼片)が無く、1本の雌蕊に雄蕊が1本だけという珍しい形の花を咲かせる。
- ヒメコウゾ

- クワ科コウゾ属の落葉低木。高さ3メートルを超えるものが1本とまだ小さく細いものが東エリアに数本有る(2024時点)。飛山池に侵入してまだ間がない様子。
- 東浦町では、たまに見かける。7月ごろ橙赤色に熟した果実が食用になるが、口当たりが良くない。和紙の原料となるコウゾの片親と言われている。



- ヤツデ

- ウコギ科ヤツデ属の常緑低木。飛山池の森では至る所にいる。
- 知多半島全域の林内の日当たりの悪いところに普通に見られる。庭木としても植えられるので、至る所で目にする機会がある。葉や花序や実が特徴的なので見つけやすい。



- ヒイラギ

- モクセイ科モクセイ属の常緑低木。飛山池では散策路沿いに1本有る(2024時点)。
- 知多半島では野生のものはあまり見かけない。公園などの植栽として見かけることがある。大きな鋸歯に鋭い棘のある葉の形が特徴的で、一見してそれと分かる。ただ、長く生きた個体は鋸歯が無い葉をつけることがある。
- ツツジの仲間

- ツツジ科ツツジ属の落葉低木。飛山池では、散策路沿いに小さい木が1本ある(2024時点)。種類は不明。葉が小さいのでサツキかもしれない。
- 常緑のツツジの仲間は、植栽として非常に多く植えられており、知多半島でも至る所で目にする。この個体のように野生状態のものがまれに見られる。
- シャリンバイ

- バラ科シャリンバイ属の常緑低木。飛山池では、散策路沿いに小さい木が1本ある(2024時点)。
- 同じバラ科の常緑樹であるビワにどことなく似た雰囲気のある樹種。海岸に自生する種属で、風や乾燥に丈夫なためよく植栽に利用される。東浦町でも公園などでよく見かける。葉は濃い緑色でほぼ無毛だが、若葉は柔らかい緑色で毛に覆われている。葉裏の葉脈の網目が非常にはっきりと見える。


- イソノキ

- クロウメモドキ科イソノキ属の落葉性小高木。飛山池では、南エリアの開けた所に1本有る。
- 東浦町では、時々見られる樹種。花期が長く一月以上の間、ポツポツと開花し続ける。そのため、果実と花芽が共存することになる。花弁に見える白い部分は萼片で全開することはなく、結果、花弁はほとんど見えない。蜜が多いようで、昆虫に人気がある。葉はサクラに似た雰囲気があるが、側脈が葉の縁で繋がっているなど細かい部分に違いがある。


- ヌルデ

- ウルシ科ヌルデ属の落葉性小高木。飛山池では、散策路沿いに時々見られる。
- 知多半島では、至る所で見られる樹種。ウルシの仲間らしい羽状複葉の真ん中の軸(葉軸)にひれ(翼)があるので、一見して本種と知れる。葉にヌルデシロアブラムシが寄生して虫瘤ができることが多く、初夏の新葉の頃はきれいだが、その後虫瘤が目立つ様になるとあまりきれいな見た目ではなくなる。この虫瘤は、五倍子(ごばいし)または付子(ふし)と呼ばれ、漢方薬や染料の原料になる。ウルシの仲間なのでウルシオールを含みかぶれることがある。ただ、含有量が少ないのでかぶれる事は少ないと言われている。

蔓
- フジ

- マメ科フジ属の蔓性落葉木本。蔓はS巻き(左手巻き)。飛山池では池沿いに大きな樹が有る。それ以外にも通路沿いで他の木に巻き付いているのが見られる。
- 東浦町に限らず知多半島では至る所に生えており、花の季節にはあの藤色で山を賑わしている。他の植物に巻き付いて締め付けるので、巻き付かれた植物が枯死することがある。日本固有種。

- サルトリイバラ

- サルトリイバラ科シオデ属の蔓性落葉木本。飛山池では散策路沿いに時々見られる。2024年時点であまり大きいものはいない。
- 東浦町に限らず知多半島では至る所に生えている。棘のある細い枝を張り巡らせて薮を作ることがあるが、ノイバラほどの巨体にならないせいかあまり目立たない。巻きひげで他の植物にしがみつく。


- アケビ

- アケビ科アケビ属の蔓性落葉木本。蔓はZ巻き(右手巻き)。飛山池ではミツバアケビと共に至る所に有る。
- 東浦町に限らず知多半島では至る所に生えている。実は食用になるのでよく知られている。花は独特の形状と質感を持ち香りも良い。小葉が5枚。
- ミツバアケビ

- アケビ科アケビ属の蔓性落葉木本。蔓はZ巻き(右手巻き)。飛山池ではアケビと共に至る所に有る。
- 東浦町に限らず知多半島では至る所に生えている。実は食用になるのでよく知られている。花は独特の形状と質感を持ち香りも良い。小葉が3枚。
- ノイバラ

- バラ科バラ属の蔓性落葉低木。飛山池では日当たりの良い通路脇に有る。
- 東浦町に限らず知多半島では至る所に生えている。つる植物だが巻き付くことはない。鋭い棘が生えており、他のものに棘を引っ掛けながらもたれかかる。バラの園芸品種の基本原種。

- アオツヅラフジ

- ツヅラフジ科アオツヅラフジ属の蔓性落葉木本。蔓はZ巻き(右手巻き)。飛山池では、日当たりの良い所には必ずと言っていいほどいる。
- 知多半島ではアケビ同様至る所に生えており、アケビやヤマノイモなど他のつる植物と絡まりながら林の縁を覆っている。花は小ぶりで目立たないが、秋に熟す果実の独特の青色が目を惹く。






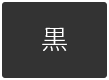

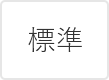
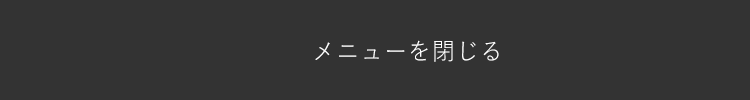









































































更新日:2025年03月19日