定額減税調整給付金 不足額給付-1
不足額給付-1とは?
「令和6年分所得税額」が確定してから、「本来給付すべき額(調整給付所要額)」と「実際に給付した額(調整給付額)」との間で差額(不足)が生じた方などへ、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

対象となりうる例
モデルケース:世帯主と扶養親族2人の3人世帯(減税対象人数 3人)

【解説】
- 令和6年分所得税の定額減税可能額は90,000円(30,000円×3人)であるが、推計所得税額は35,000円であった。減税可能額から推計所得税額を差し引いた55,000円が所得税分の控除不足額(減税しきれない額)となる。
- 令和6年度分個人住民税所得割の定額減税可能額は30,000円(10,000円×3人)であるが、税額は22,000円であった。減税可能額から実際の税額を差し引いた8,000円が住民税所得割分の控除不足額(減税しきれない額)となる。
- 控除不足額の合計は63,000円(55,000円+8,000円)となり、これを1万円単位で切り上げた70,000円が調整給付の支給決定額となる。
例1 令和5年分所得よりも、令和6年分所得が減少した場合

【解説】
- 令和6年分所得税の実績は27,000円で、推計所得税額よりも減少したため、所得税分の控除不足額は、減税可能額である90,000円から実績の所得税である27,000円を差し引いた63,000円に変更となる。
- 令和6年度分個人住民税所得割の額に変更はないため、控除不足額8,000円は変更がない。
- 控除不足額の合計は71,000円(63,000円+8,000円)に変更となり、1万円単位で切り上げた80,000円が不足額給付における調整給付所要額となる。
- 不足額給付における調整給付所要額80,000円から、調整給付の支給決定額70,000円を差し引いた10,000円が不足額給付の支給決定額となる。
例2 令和6年中に扶養親族数が増えた場合

【解説】
- 令和6年中に扶養親族が1人増えたため、令和6年分所得税の減税対象人数は4人に変更となる(令和6年度分個人住民税所得割の減税対象人数は、令和5年12月31日時点での判定となるため、3人のまま変更はない。)。
- これに伴い、令和6年分所得税の定額減税可能額は120,000円(30,000円×4人)に変更となる。
- 令和6年分所得税の実績は27,000円で、推計所得税よりも減少したため、所得税分の控除不足額は、減税可能額である120,000円から実績の所得税である27,000円を差し引いた93,000円に変更となる。
- 令和6年度分個人住民税所得割の額に変更はないため、控除不足額8,000円は変更がない。
- 控除不足額の合計は101,000円(93,000円+8,000円)に変更となり、1万円単位で切り上げた110,000円が不足額給付における調整給付所要額となる。
- 不足額給付における調整給付所要額110,000円から、調整給付の支給決定額70,000円を差し引いた40,000円が不足額給付の支給決定額となる。
例3 令和5年中の申告内容に変更があり、令和6年度個人住民税の修正申告等をしたことにより、個人住民税所得割が減少した場合

【解説】
- 令和6年分所得税の額に変更はない(注)ため、控除不足額55,000円に変更はない。
(注)修正申告等をしたのは令和5年分の申告内容についてであるため、令和6年分所得税の額には影響がない。
- 令和6年度分個人住民税所得割は、税額決定後に修正申告があり、税額が14,000円に減少したため、令和6年度分個人住民税所得割の控除不足額は、減税可能額である30,000円から修正申告後の税額である14,000円を差し引いた16,000円に変更となる。
- 控除不足額の合計は71,000円(55,000円+16,000円)に変更となり、1万円単位で切り上げた80,000円が不足額給付における調整給付所要額となる。
- 不足額給付における調整給付所要額80,000円から調整給付の支給決定額70,000円を差し引いた10,000円が不足額給付の支給決定額となる。
通知発送・確認方法
対象者であることが確認できた方には、9月1日付けで「支給のお知らせ」または「支給確認書」のいずれかの書類を送付しました。
支給のお知らせ(手続き不要)
次の1、2のいずれかに該当する場合は、「支給のお知らせ」を送付します。
- 令和6年度の調整給付金を口座振込で受給した場合(代理受給した場合は除く。)
- マイナンバーカードで公金受取口座を登録済みの場合
「支給のお知らせ」が届いた方は、書類提出の手続きは必要ありません。
なお、給付金を受給しない場合や、振込口座を変更する場合及び支給のお知らせに記載の各数値について重大な相違を認める場合は、税務課(0562-83-3111)へご連絡ください。
支給確認書(書類の返送が必要)
「支給のお知らせ」の送付要件に当てはまらない方には「支給確認書」を送付します。確認書が届いた方は、令和7年10月31日(消印有効)までに確認書及び必要書類を返送してください。返送期限までに返送がない場合は、支給を辞退したとみなします。
支給確認書を返送する際の注意点
- 書類を返送する際は、同封の返信用封筒をご利用ください。提出された書類はお返ししませんので、ご了承ください。
- 同封の「記入例」をご確認いただき、漏れのないようにご記入ください。
- 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)は氏名、生年月日、住所を確認できる部分の写し(コピー)としてください。引越し等により住所が変更されている場合は、最新の住所を確認できる面の写し(コピー)の提出も必要です。
- 振込先口座確認書類は、通帳の表紙を開いた1ページ目の写し(コピー)等、振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を確認書に添付してください。
- 振込先口座について、長期間入出金のない口座は添付しないでください。
- 記入漏れ・チェック漏れや、提出書類の不備がある場合、給付を受けられません。
支給時期
「支給のお知らせ」が届いた方
お知らせに記載の振込日・口座へ振り込みます。
「支給確認書」が届いた方
確認書提出日から約30日後を目安に、確認書で指定された口座へ振り込みます。なお、振り込み前に振込日及び振込口座を記載した「払込のお知らせ」を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
税務課 住民税係へメールを送信




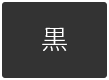

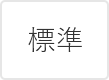
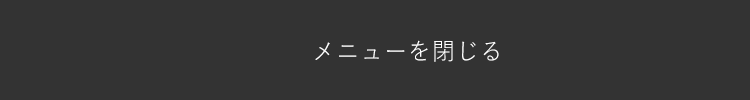
更新日:2025年09月03日