高額療養費
2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により高額療養費として後から支給されます。高額療養費の支給対象となる方には、診療月の3か月程度後に申請書を同封した案内通知を送付しています。郵送で手続きされる場合は、申請書に必要事項を記入し、保険医療課まで返送してください。郵送時の切手代は、申請者のご負担となります。
【大切なお知らせ】支給申請手続きの簡素化が始まります
高額療養費の支給申請手続きの簡素化が始まります。「簡素化申請書」を提出するだけで手続きは完了し、2回目以降の診療月毎の申請書を提出する必要はなくなります。該当する方には令和5年1月発送分から順次『簡素化申請書』を発送します。詳細は次をご覧ください。
診療月毎の申請書を来庁して手続きする場合に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1点
- 送付した診療月毎の申請書
- 預金通帳等(世帯主又は療養を受けた者)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び療養を受けた者)
- 来庁する方の本人確認書類
- 領収書(注1)
(注1)申請書に「領収書のコピーを添付してください」と押印されている場合は、該当する医療機関が発行した領収書をお持ちください。(難病等公費による治療を受けた場合)
(注) 別世帯の方が手続きされる場合は委任状(PDF:76.9KB)が必要です。
(注) 世帯主が亡くなり、相続人の方が手続きされる場合は誓約書(PDF:94.4KB)が必要です。
本人確認書類とは
公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
または
その他(下記の中から2点)
健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等
時効
診療月の翌月1日から2年
70才未満の自己負担限度額(月額)
| 区分 |
所得要件(注1) |
自己負担限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) |
|---|---|---|---|
| ア |
901万円超 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ |
600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ |
210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ |
210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)所得とは、「基礎控除後の総所得金額」のこと。
- 所得の申告がないと、自己負担額は最も高い金額で計算されます。所得がない場合も税法上の扶養になっていない場合はゼロ申告が必要です。
- 限度額4回目以降とは:同一世帯で高額療養費に該当する月が、その月を含めて過去12か月に4回以上あるときは、4回目以降の自己負担限度額になります。
自己負担額の計算にあたっての注意
- 月の1日から末日まで、各月ごとの受診について計算します。
- 同じ医療機関でも、医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となります。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
70才未満の人の合算について
同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた金額が支給されます。
70才以上の高額療養費と自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来及び入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
3(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円(注4)】 |
|
| 2(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円(注4)】 |
||
| 1(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円(注4)】 |
||
| 一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円(注2) |
57,600円 【44,400円(注)3】 |
|
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | |
(注2)外来年間(8月から翌年7月)の限度額は、144,000円です。一般、低所得者1、低所得者2だった月の自己負担額の合計に適用します。
(注3)その月を含めて過去12か月以内に外来及び入院(世帯単位)の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。
(注4)その月を含めて過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。
自己負担限度額の計算にあたっての注意
- 月の1日から末日まで、各月ごとの受診について計算します。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は70才以上75才未満の方の医療費を合わせて計算します。
- 病院・診療所、歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
75才到達月の患者負担の限度額の特例について
国民健康保険の加入者が75才になって後期高齢者医療制度に移る場合又は社会保険の加入者が75才になってその配偶者が国民健康保険に加入する場合は、その月の自己負担限度額は通常月の2分の1になります。
70才未満の人と70才以上75才未満の人が同じ世帯の場合の合算
合算の計算方法は次のとおりです。
1 70才以上75才未満の人の限度額をまず計算
2 1に70才未満の人の合算対象額を加える
3 70才未満の人の限度額を適用して計算
入院など、一つの医療機関への支払いが高額になるとき
70才未満の人、70才以上で現役並み所得の方及び住民税が非課税の方が高額な医療を受ける場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると窓口負担は自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きはこちらです。
マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関等で同意することにより「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」として利用できますので、申請は必要ありません。また令和7年8月1日以降は、マイナ保険証の人にはこれらの認定証を発行することができません。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
保険医療課 保険年金係へメールを送信




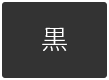

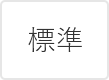
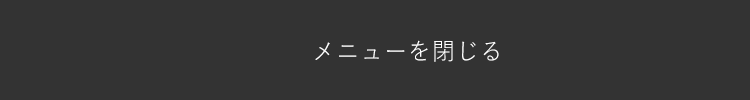
更新日:2021年04月01日