学校給食週間について
1月24日から1月30日までは、全国学校給食週間です
学校給食は、明治22年に始まって以来、各地に広がっていきましたが、戦争の影響などによって中断されました。
戦後、子どもたちの栄養状態を改善するために、昭和21年6月に米国のLARA(アジア救済公認団体)から、給食用物資の寄贈を受けて、昭和22年1月から学校給食が再開されました。
昭和21年12月24日に、東京都内の小学校でLARAからの給食用物資の贈呈式が行われ、それ以来、この日を「学校給食感謝の日」と定めましたが、冬休みと重なってしまうことから、1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。
子どもたちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態に懸念される点が多く見られる今日、現在の学校給食は、子どもたちの心を豊かにし、食に関する正しい知識と望ましい食生活を身に付けるための健康教育の一環として、重要な役割を担っています。
学校給食週間においては、このような学校給食の意義や役割に関して、児童生徒や教職員、保護者や地域住民の理解を深め関心を高めるため、全国でさまざまな行事が行われます。
(参考:文部科学省ホームページ)
東浦町学校給食センターの変遷
昭和47年5月 第1給食センター(旧)開設
昭和55年4月 第2給食センター(旧)開設
(注)跡地には、現在役場東防災倉庫が建っています。
↓
平成26年4月 東浦町学校給食センター(現)開設
↓
令和4年4月 調理・配送・洗浄業務の民間委託開始

現在、約4,600食の給食を作っています!
給食週間の献立紹介 テーマ「アジア各国の料理を味わおう!」
~アジア競技大会・アジアパラ競技大会開催記念~
26日(月曜日)中華人民共和国
<ハオユーニューロウ>
牛肉と野菜を炒めて、オイスターソースで味付けします。
<バンサンスー>
「バン(和える)、サン(数字の3)、スー(糸)」で「糸のように細く切った3種類の食材をあえる」という意味です。
<パーパオツアイ>
おなじみの「八宝菜」です。 肉、魚介類、うずら卵、野菜など、たくさんの食材を合わせて、炒め煮にします。
27日(火曜日)フィリピン共和国
<ポークメヌード>
「メヌード」はフィリピンの言葉で「小さいかけらに切り分ける」を意味します。豚肉、にんじん、じゃがいもなどをトマトソースで味つけして煮込んだフィリピンの伝統的なシチューです。
<パンシットビーフン>
誕生日や結婚式などお祝いごとのある時に食べることの多い麺料理です。鶏肉、野菜、ビーフンを炒めて、「パテイス」(魚を塩漬けにして発酵させて作る調味料)で味をつけます。
<フルーツサラダ>
ナタデココやフルーツを生クリームとコンデンスミルクであえたデザートです。
28日(水曜日)大韓民国
<キンパ>
韓国の言葉で、「キム」はのり、「パプ」はごはんを意味します。肉や野菜を具にして、のりで巻いて食べます。
<ヤンニョムチキン>
ヤンニョムという甘辛いソースをからめた鶏肉の唐揚げです。韓国のファーストフードから始まりました。
<トゥブチゲ>
「チゲ」とは韓国の言葉で「鍋料理」を意味します。具や味つけはいろいろで、辛いものも辛くないものもあります。
29日(木曜日)ベトナム社会主義共和国
<バインミー>
ベトナムのサンドイッチです。パンに肉やハム、甘酢に漬けた野菜などをはさんで食べます。地域やお店によって、さまざまな種類があります。
<フォーガー>
ベトナムの言葉で「フォー」は米粉から作られた平たい麺を、「ガー」は鶏肉を意味します。伝統的な麺料理でさっぱりとした味つけです。主に朝食で食べられています。
<コーヒー牛乳の素>
ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国です。コーヒーは甘いミルクを入れてデザート感覚で飲むことが多いです。す
30日(金曜日)日本国
<みそおでん>
愛知県の郷土料理です。肉、魚(練り製品)、卵、大豆製品(生揚げ)、野菜と多種類の食材を合わせて、知多半島で作られた豆みそで煮込んでつくります。
<キャベツのゆかりあえ>
給食で大人気のあえものです。知多半島産のキャベツを使用しています。
<おにまんじゅう>
愛知県の郷土料理です。愛知県産のさつまいもを使い、給食センターで1個ずつ手作りします。
この記事に関するお問い合わせ先
教育課 給食係(東浦町学校給食センター)
〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字三ツ池一区7番地
電話番号:0562-83-5314
教育課 給食係へメールを送信




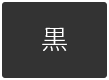

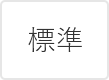
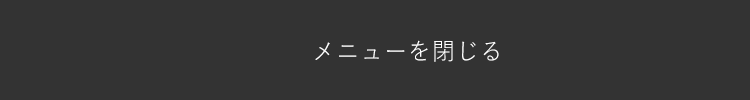
更新日:2024年01月24日